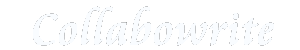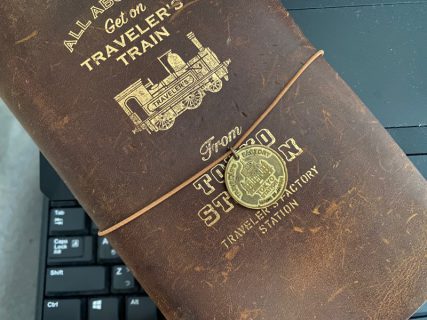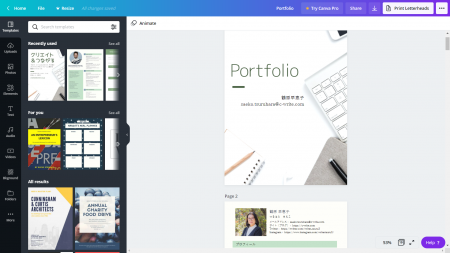インタビュー音源をそのまま文字起こししたって、記事にはなりません。読者に読みやすいように、きちんと「記事」としての体裁を整えるという作業が必要です。
そこで今回は、インタビュー取材後に音源を「記事」にする方法について、私のやり方を少しご紹介します。
今回のポイント
なにはともあれ、まずは文字起こし
どんな体裁の記事にするにせよ、まずするべきことは文字起こしです。文字起こしの方法は人によって、あるいは案件によって違います。
文字起こしについては、以前ブログに書いたように、私は基本Amazon Transcribeでざっくり文字起こしをして、そのあとokoshiyasu2で聞き直しつつ、自分で不十分なところを埋めていくというスタイルをとってます。
インタビュー時の音源文字起こしを自動化したい!と無料&有料ソフト、AmazonTranscribeを試してみた結果│コラボライト
ただ、人によってはシャドーイング(音声を聞きながらその場で自分で復唱する方法)をしてGoogleドキュメントの音声入力を使う人もいます。このあたりは、自分にあった方法でいいと思います。
文字起こしについては、一語一語正確にするようにはしています。ただし、たとえばインタビューというよりヒアリング(サイトに乗せる文章の主旨をざっくり聞くようなレベル)の場合は、箇条書きというかメモというか、要点だけをざっと書き取った簡略版文字起こしで済ませるケースもあります。このあたりは案件によりけりです。
文字起こしをしたら、どういう体裁の記事にするか決める
文字起こしをしたら、どういう体裁の記事にするかを決めます。記事の体裁は、大きくわけて3つ。
1.その人がしゃべっているように書いたもの
2.地の文とセリフを織り交ぜたもの
3.しゃべり言葉を完全になくしたもの
どれにするかは、自分で決められる場合もあれば、クライアント様に指定されることもあります。それぞれの体裁について、ちょっと説明しますね。
その人がしゃべっているように書いたもの
たとえば、その人がしゃべっているように書いたものであれば、こんな記事があります(私が書いた記事です。名前は出ていませんが、公開の許可はいただいています)。
【第3回】匠弘堂の見学に来られる方に、私が必ず伝えていること│京都 社寺建築 匠弘堂
複数で喋っている場合は、こんな感じの記事になりますね。
鑿(のみ)鍛冶と宮大工が語る、仕事や道具への思い~産地の祭典トークショーレポート(前編)│京都 社寺建築 匠弘堂
地の文とセリフを織り交ぜたもの
地の文とセリフを織り交ぜたものは……うーん、ちょっと今出せる実績がないのですが……たとえば
「こういういう事情があるんですよ。本当に困りましたね」
みたいなAさんの言葉を
この背景には、こういう事情があった。
「本当に困りました」とAさんはそのときのことを振り返り、こう語る。
みたいな書き方で文章化するものです。こういう記事も書いたことがあるのですが、ちょっとわけあって実績として紹介することができません、申しわけありません。
しゃべり言葉を完全になくしたもの
しゃべり言葉を完全になくしたものというと、和樂webに掲載したこの記事が近いかもしれません。
切れ味も美しさもここから生まれる!刃物を使う職人を支える天然砥石の魅力 │ 和樂web 日本文化の入り口マガジン
これは、取材協力いただいた方に天然砥石についてお話いただいて、それに私がリサーチた内容も含めて記事化しています。
記事の構成に合わせて、文字起こしの内容を編集する
どんな体裁の記事にするか決めたら、記事の構成を決めます。一般的には時系列に沿って構成するので、そんな難しいことではありません。
ただ、実際に取材をして音源を聞き返していると、話の内容が「A→B→C→B’→A’→C’」というように、あっちにいったりこっちにいったり、ループしたりするケースがあるんですよね。
あるいは、取材の最中にまったく記事のテーマから外れた話が入ってくることも。
そんな場合、そのまま時系列で記事を書いてしまうと、とりとめのない、いまひとつよくわからない内容になってしまう可能性がとっても高くなります。
そこで、必要に応じて「A→A’→B→B’→C→C’」と時系列を前後させ、テーマから外れた内容をばっさり削って……と、文字起こしの内容を編集します。
最後は、インタビュイーチェック!
文字起こしの内容を編集したあとは、記事として読みやすくなるようにさらに体裁を整えます。必要に応じて注釈を入れたり、そのまま記事にするには不適切な言葉を調整することもあります。
そして、最後にインタビューを受けてくださった方に原稿を見ていただき、チェックをしていただきます。
インタビュイーにチェックしてもらう理由
チェックをしていただくのは、内容に間違いがないか、その人にとって不適切な話や表現はないかなどを確認していただくため。
ここで、インタビュイーの方から好意的な言葉が返ってくるとすごくほっとします。
というのが、取材記事って、書いている間ずっと「これでいいのかな、取材対象の方のおっしゃりたいこと、私はきちんと理解して、汲み取って書けているのかな」って不安なんですよ。チェックお願いした瞬間も、「全然だめです」とか言われたらどうしよう?ってめちゃくちゃ怖いんですよ。
チェックバックがあったときも、メール開封するのが怖くて怖くてしょうがなくて、ちょっと意味なく部屋の中うろうろして心落ち着けてようやくクリックできるんですよね。ひどいときはベッドの上にごろごろ寝転がって、ぶつぶつひとりごと言って気持ちを紛らわせながらスマホで開封して薄目でざっと本文を見る、みたいなときも(すごいチキンハートだな)。
その不安や恐怖が解消される瞬間なので、そりゃあもう安心するなんてレベルじゃありません。
そして、チェックバックを確認して原稿を修正・調整し、クライアントに納品する……というわけです。
チェックを省略するケースもあります
なお、速さを重視する報道系の記事の場合は、チェックを省略して記事を公開することもあります。こういうときは、普段のインタビュー記事以上に神経を使います。きちんと録音して、なるべく文字起こしそのままの言葉を使うようにして、言った言わない系のトラブルにならないよう、万一そうなったときもきちんと証拠を示せるようにしています。